バッテリー発火問題への対策とその余波?
GoogleのPixelシリーズでは、特に2022年発売のPixel 6aにおいて、充放電の繰り返しによるバッテリー劣化が進み、一部のケースでは異常発熱から発煙や発火に至ったとの報告が複数寄せられています。これを受けてGoogleはPixel 6a向けにバッテリーの無償交換を実施するとともに、充放電性能を犠牲にしてスマートフォン全体の性能を引き下げるアップデートを配信しました。
この経験を踏まえ、GoogleはPixel 6a以降の機種に「バッテリーの健全性アシスタント」という新機能を搭載しました。この機能は、一定の充電サイクルを超えた後にバッテリーの最大電圧を調整し、寿命を最大限維持できるようにする仕組みです。
しかし、この「バッテリーの健全性アシスタント」について、Pixel 10シリーズからはユーザーが無効化できない仕様で強制的に有効化されることが明らかになりました。
200回以降の充放電からPixel 10のバッテリー性能が変化。充電速度低下などが発生?
Android Authorityの報道によると、GoogleはPixel 10シリーズから「バッテリーの健全性アシスタント」をユーザーが無効化できない形で実装することを認めています。
この機能は「バッテリー劣化の安定化」を目的とし、200回目以降の充放電サイクルから段階的に有効化され、1000回に達するまでの間にソフトウェア制御でバッテリーの最大電圧や充電速度を抑制していきます。
そのため、ユーザーは特に設定を行わなくても、200回以降の充放電からは充電にかかる時間が長くなり、バッテリーの持続時間も徐々に短くなるといった変化を体感することになります。
Pixel 9aなら許されるがPixel 10では微妙?
この「バッテリーの健全性アシスタント」はPixel 9aから搭載されており、この機種でも無効化はできずバッテリーの充放電サイクルに応じて性能を意図的に低下させる機能が備わっていました。ただ、Pixel 9aはエントリーモデルでありコストが安いバッテリーの採用や、製品寿命を重視する設定にすることは許容できると言えます。
しかしPixel 10シリーズは、最廉価モデルでも10万円を超えるハイエンド機です。性能を重視するユーザー層が多いため、バッテリー寿命よりもパフォーマンスや高速充電を優先したいというニーズは少なくないでしょう。そうしたユーザーにとって、バッテリー性能制限の強制適用は歓迎されない可能性があります。
また、競合スマートフォンのバッテリー性能もサムスンではバッテリー容量が80%まで落ちるのに約2000回の充放電サイクル、OnePlusやOPPOは1600サイクと長寿命化が行われている一方で、Pixel 10シリーズは1000回で80%程度に落ちると言うのはバッテリー性能に関して特に耐久性の観点で競合より大きく劣っていることは明白であるため、今回のGoogleの判断についてユーザーから批判を集めてしまう可能性がありそうですが、このGoogleはこの方針を維持するのか、柔軟な対応に切り替えるのか注目が集まりそうです。



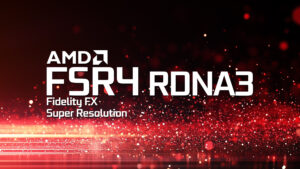





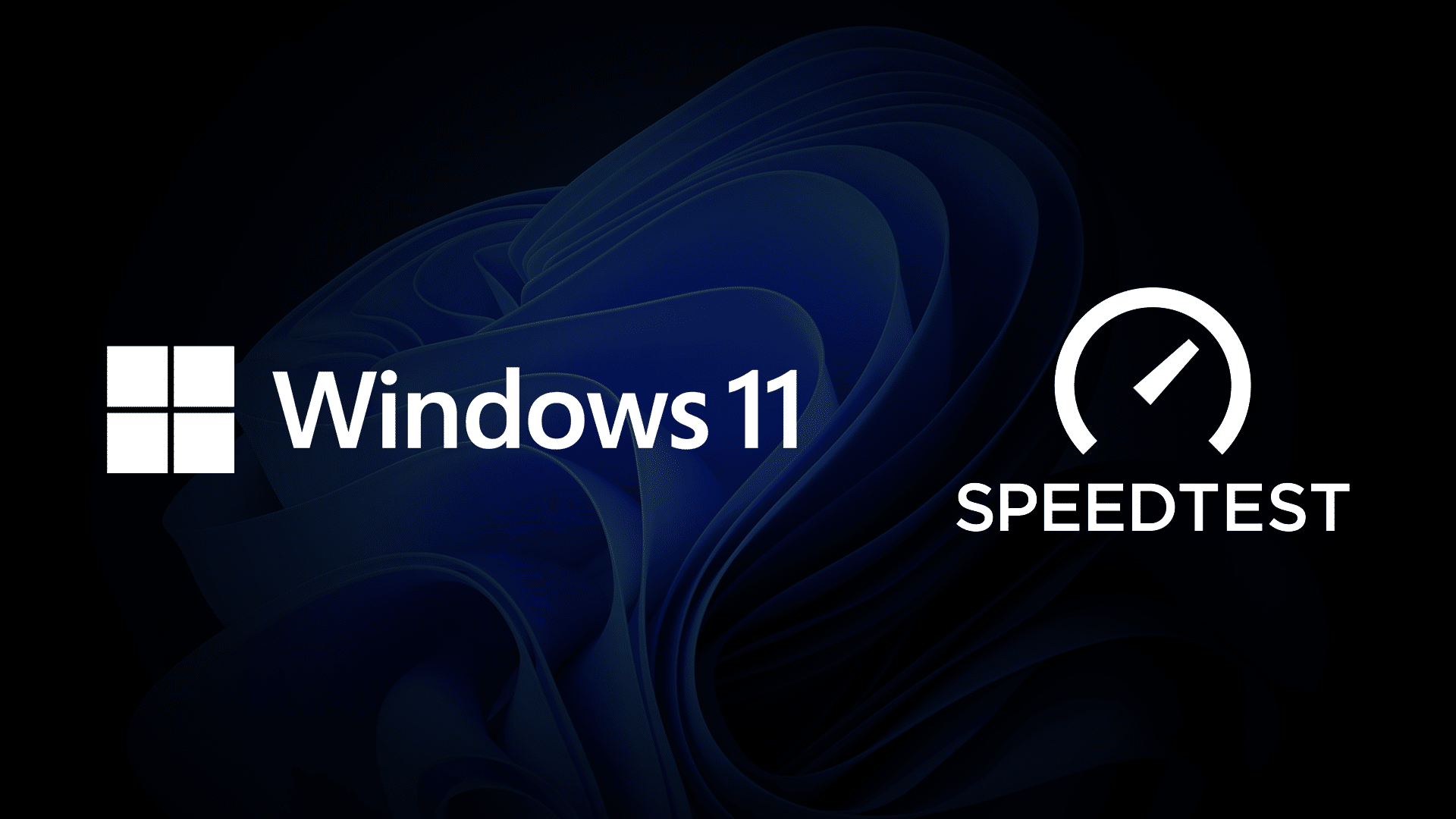



コメント