AMD Zen 6 リーク情報まとめ|性能・アーキテクチャ・発売日について
AMDは2024年に投入したZen 5アーキテクチャの後継CPUであるZen 6アーキテクチャの開発を進めていると言われており、これらは2026年に発売されるといわれています。
ここではそんなZen 6について公式発表までの間に現時点で明らかにされているリークや噂などを一挙にまとめて紹介していきます。
最終更新日:2025年8月9日
現時点で判明しているZen 6のリーク情報まとめ
| 仕様 | デスクトップ向け | ノートPC向け |
|---|---|---|
| 登場時期 | 2026年10月~12月 | 2027年1月~3月 |
| 製造プロセス | TSMC 2nm / 3nm | TSMC 2nm / 3nm |
| 変更規模 | CCDの構造変更(コア数増) IODの構造変更 | CCDの構造変更(コア数増) IODの構造変更(チップレット採用) |
| コア数 | 最大24コア 標準12コア | 最大24コア 標準12コア |
| プラットフォーム | ソケットAM5 | ー |
| 内蔵GPU | RDNA 3.5 | RDNA 3.5 |
Zen 6の最新リーク情報一覧
記事が見つかりませんでした。
Zen 6のアーキテクチャ|Zen 5からの進化点について
Zen 6アーキテクチャは現行のZen 5や先代のZen 4に対してCPUアーキテクチャの刷新は当然含まれますが、長年変更されてこなかったI/OダイとCPUダイ(CCD)の接続方式を見直すなどCPUアーキテクチャのみならず、通信方式など今までのZenアーキテクチャに対して大きく変更されるポイントが多くなっています。
アーキテクチャの変更点
Zen 6はアーキテクチャはZen 5に対してCPUコア含めて大幅な刷新が行われると言われていますが、現時点でアーキテクチャそのものに関するリークは出ていません。ただ、アーキテクチャの性能に大きく関係する製造プロセスはデスクトップやノートPC向けのハイエンド製品にはTSMC 2nmを採用し、メインストリーム向けノートPC製品にはTSMC 3nmを活用すると言われています。
AMDのデスクトップ向け Zen 6 の一部スペックがリーク。最大24+2コアで6.0 GHzで動作
また、製造プロセス微細化などにより各CCDに含まれるコア数が増える見通しで、現行Zen 5の8コアから12コアに増やされる見込みです。これにより特にデスクトップ向けではZen 2以来のコア数増になります。
チップレット構造とI/Oダイ(IOD)の刷新
デスクトップ向けZen 6ではZen 2アーキテクチャ登場以降あまり手がつけられてこなかったI/OダイとCCDとの接続方法が大きく変更されると言われています。
現行のデスクトップ向けZen 5などはI/OダイとCCDが基板上に配線されるSERDES (Serializer / Deserializer)と呼ばれる方法が用いられています。この接続方法は信号の信頼性が高く、データの転送率を高くできるものの、レイテンシが高いというデメリットがありました。このデメリットに関してはZen 4までは顕在化してこなかったものの、Zen 5などはCPU性能向上によりこのレイテンシがボトルネックに繋がっていると指摘が出ています。
しかし、Zen 6ではI/OダイとCCDの接続をブリッジダイで繋ぐFan-out Embedded Bridge (FOEB)へ変更される見通しです。このFOEBはすでにStrix Haloなどでも用いられており、この変更により帯域幅の大幅向上に加え、I/OダイとCCDが隣り合わせになることで配線長の短縮などレイテンシの大幅低減を実現すると見られています。これにより抜本的な性能向上に加え、特に非3D V-CacheモデルのCPUでもゲーミング性能の大幅向上が期待ができます。
Zen 6の性能|ラインアップとスペック
登場予定のラインアップとスペック
AMDのZen 6を搭載する製品はデスクトップ向けからノートPCまで幅広くラインアップされる見込みで、それぞれ登場するラインアップにコードネームが付けられています。
| フォームファクター | コードネーム | コア数 | 登場時期 |
|---|---|---|---|
| デスクトップ向け | Olympic Ridge | 最大26コア | 2026年秋 |
| ノートPC向け | Medusa Point Big/Little | Big = 22コア Little = 12コア | 2027年1月以降 |
| ノートPC向け 廉価モデル | Bumblebee | 6コア | 2027年以降 |
| ノートPC向け 最上位モデル | Medusa Halo | 最大26コア | 開発中止? |
デスクトップ向け:Olympic Ridge
デスクトップ向けは過去のZen系と同じく『Ridge』がつくコードネーム「Olympic Ridge」という名称が付与されています。
コア数はCCD内に含まれるコアが12コアに増えることに加え、I/Oダイには省電力コアが2コア内蔵されると言われています。そのため、ベーシックでCCDを1基搭載するRyzen 7シリーズは8コアから12コア、CCDを2基搭載するRyzen 9シリーズでは最大16コアから24コアに増えると言われています。
AMDのデスクトップ向け Zen 6 の一部スペックがリーク。最大24+2コアで6.0 GHzで動作
動作クロックもTSMC 2nmを採用することで大きく向上すると言われており、ブースト時の最大クロックは6.5 GHzを超え、7 GHzに迫ることを目標に開発が進められているようです。
AMD Zen 6 の動作クロックは7GHzが目標。高クロック化で性能を伸ばす方針?
ノートPC向け上位:Medusa Point
現行のZen 5世代ではハイエンドモデル向けがStrix Point、メインストリーム向けのKrakan Pointと分けられていますが、Zen 6ではすべてMedusa Pointに統合されます。しかし、性能面での差別化を図るため、メインストリーム向けのMedusa Point (Little)に対して、ハイエンド向けに投入されるMedusa Point BigはモノリシックダイにCCDを追加することでCPU性能の大幅向上を図っています。
AMDの Zen 6 搭載APUのラインアップやスペックがリーク。一部モデルはRDNA5 (UDNA) を搭載する可能性も
基本となるMedusa Point LittleはCPUと内蔵GPUを1つのダイに収めたモノリシックダイで、CPUは省電力コアのZen 5d (Dense)を4コア、高性能コアのZen 5c (Classic)を4コアと超低電力コアを2コアの合計10コアを備えます。内蔵GPUはRDNA 3.5+アーキテクチャで構成される8基のCompute Unitを備えます。
これは現行のKrakan Pointに対して、コア数は8コアから10コアに増えるため性能向上に期待できる内容になっています。
ハイエンド向けのMedusa Point Bigは上記のLittle構成に対して、12コアのZen 5dを内蔵したCCDを追加するモデルでコア数は合計22コアに達するモデルになります。
AMD Zen 6 搭載 Medusa Point のスペックが判明。ノートPC版は最大22コア | GAZLOG
ただ、このMedusa Point Bigも内蔵GPUは8基のCUしか備えないため、Zen 5世代のRyzen AI 9 HX 370に対しては劣るため、CUを現行同等の16基搭載したモデルも投入されると考えられますが、現時点でそれらのモデルの存在は確認されていないようです。
ノートPC向け廉価版:Bumblebee
AMDはChromebookや廉価なWindowsノートPC向けにBumblebee(ミツバチ)と呼ばれる新しいAPUの投入を計画しています。
同APUはZen 6dとZen 6cと省電力コアをそれぞれ2コアづつ搭載し、合計6コア構成になります。内蔵GPUは2~4基のRDNA 3.5+を搭載するなど最小限の構成になっています。
AMDの Zen 6 搭載APUのラインアップやスペックがリーク。一部モデルはRDNA5 (UDNA) を搭載する可能性も
ノートPC向け最上位:Medusa Halo
Medusa Haloは「Halo」系ということでZen 5世代から投入された内蔵GPUを大幅強化したAPUで、デスクトップ向けの12コアCCDを最大2基とI/Oダイ内に内蔵の省電力コアを2コアで合計26コアを持つCPUになっています。また、売りの内蔵GPUはRDNA 3.5+が引き続き採用されますが、CUは48基に増えるなどさらなる高性能化が期待されていました。
しかし、最も直近のリークではMedusa Haloの開発が中止されたという話もあるため今後の動向に注目が集まります。
AMD、Zen 6世代の高性能APU『Medusa Halo』を開発中止?ロードマップから姿を消す
3D V-Cacheモデルはキャッシュ容量が増加へ
Zen 6世代でもゲーミングに特化した3D V-Cacheモデルが投入される計画ですが、長らく変わっていなかった3D V-Cache容量がZen 6世代から増える見通しです。
リークではZen 6の3D V-Cacheは現行の64MBから96MBに変更される見込みで、これにより通常のCCD1基のみ搭載するモデルではCPU内蔵のL3キャッシュ48MBに加え、96MBが追加されることで156MBに増加します。
Ryzen 9 9950X3Dのように2つあるCCDの内、片側にのみ3D V-Cacheを搭載する場合は合計216MB、両側を3D V-Cache化した場合は288MBとZen 5世代を大幅に上回るキャッシュ容量を持ちます。
なお、技術的にはZen 6に搭載される3D V-Cacheは最大2層まで積み重ねることも可能なようですので、仮に2層重ねた仕様ではCCD1基のみ搭載するモデルで240MBのL3キャッシュを持つことが可能になりますが、この仕様は競合IntelのNova LakeもbLLCと呼ばれる大容量キャッシュを備えたCPUを計画しているため、このCPUの競争力次第ではAMDも2層3D V-Cacheなどを投入するかもしれません。
AMD Zen 6 の3D V-Cacheは最大240MBのL3キャッシュを搭載可能な設計
Zen 6の発売日と対応ソケット
AMDのロードマップから見る登場時期
AMDは例年、デスクトップ向けは秋、ノートPC向けは年初に発売するスケジュールをZen 3世代から続けているため、Zen 6でも同様のスケジュールで発売されることが予測されています。
そのため、デスクトップ向けは2026年秋(9月から11月)に発売され、ノートPC向けは2027年開催のCES 2027で発表される流れになると考えられます。
対応ソケットはAM5を継続
デスクトップ向けZen 6では2022年から投入されているソケットAM5が引き続き使用できます。ただし、Zen 6のI/Oダイ刷新と同時にメモリーコントローラー(IMC)も新世代化されることが明らかになっています。
AMD Zen 6 は一部の2DIMMマザーボードで起動しない可能性? 新メモリーコントローラーが影響か
これに伴い従来のX670、B650、X870、B850などのマザーボードの中でDDR5スロットを2つしか搭載しないモデルではパフォーマンスの低下や最悪の場合は互換性問題などが発生する可能性が指摘されています。
そのため、使っているマザーボードにDDR5スロットが2つしか備わっていない場合は最高性能を発揮させるには買い替えなどが求められる可能性が少なからずあるようです。一方で、4つのDDR5スロットを持っているマザーボードの場合は刺す位置を変えるだけで良いため、影響はないようです。
Zen 6まで待つかどうか?
Zen 6ではCPUコアが最大26コアに増えたり、I/Oダイの構造が刷新されるなど大幅な性能向上が期待できるCPUになっています。そのため、例えば現在AMDのソケットAM4世代のZen 2やZen 3などを使っているユーザーなどは買い替え候補として、Zen 6登場まで待ってもいいかもしれません。また、Intel製CPUであればCommet LakeやAlder Lakeからの買い替えにもZen 6は最適かもしれません。
一方で、AMDのZen 4世代、IntelのRaptor Lake以降の世代のCPUを持っているユーザーの場合はZen 6に買い替えることで得られる性能差は例えば動画編集やレンダリングなどCPU重視のタスクであれば影響はあると考えられますが、ゲーミングにおいてはあまり大きな差を感じることはできないと考えられます。
ただ、注意点としてZen 6に対抗して登場するIntelのNova Lakeシリーズではゲーミング向けに大容量キャッシュであるbLLCを搭載するCPUのほか、コア数が最大52コア化されるなど競争力が大きく高められると言われています。そのため、Zen 6を狙っている人でもIntel Nova Lakeの動向にも注目しておいたほうがいいかもしれません。





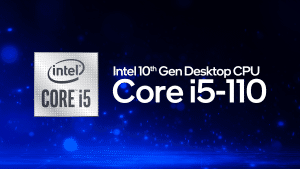


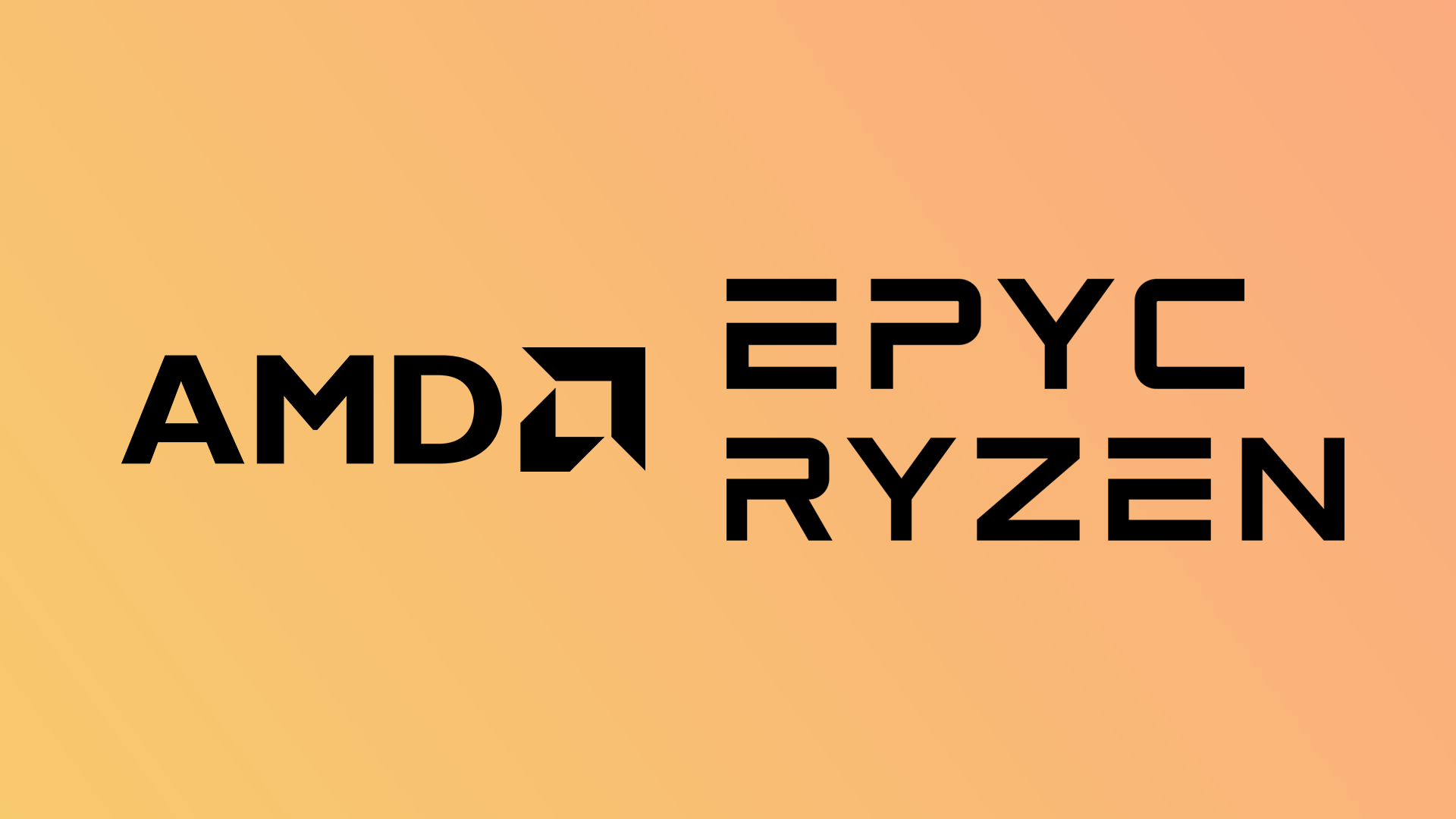

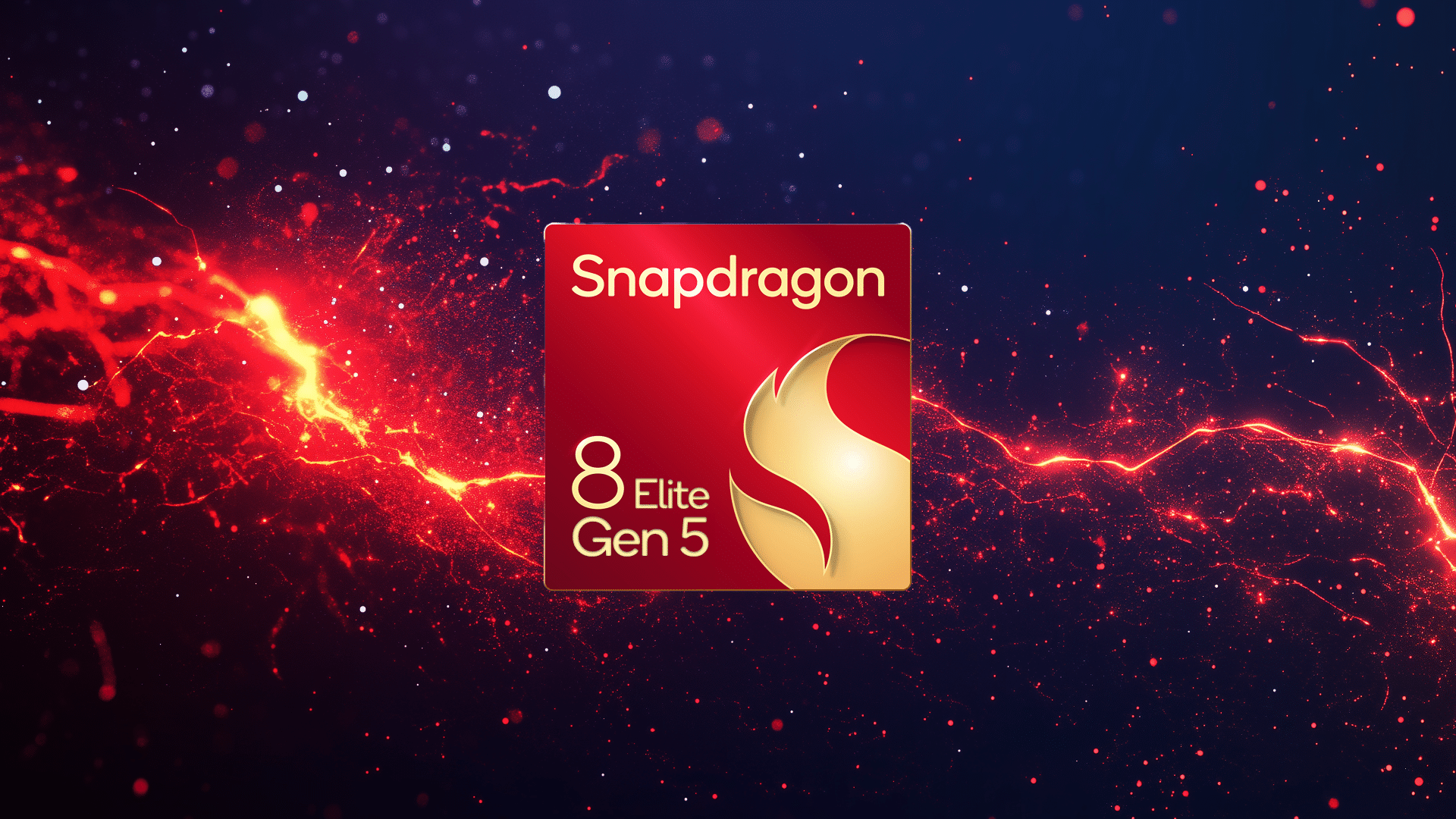
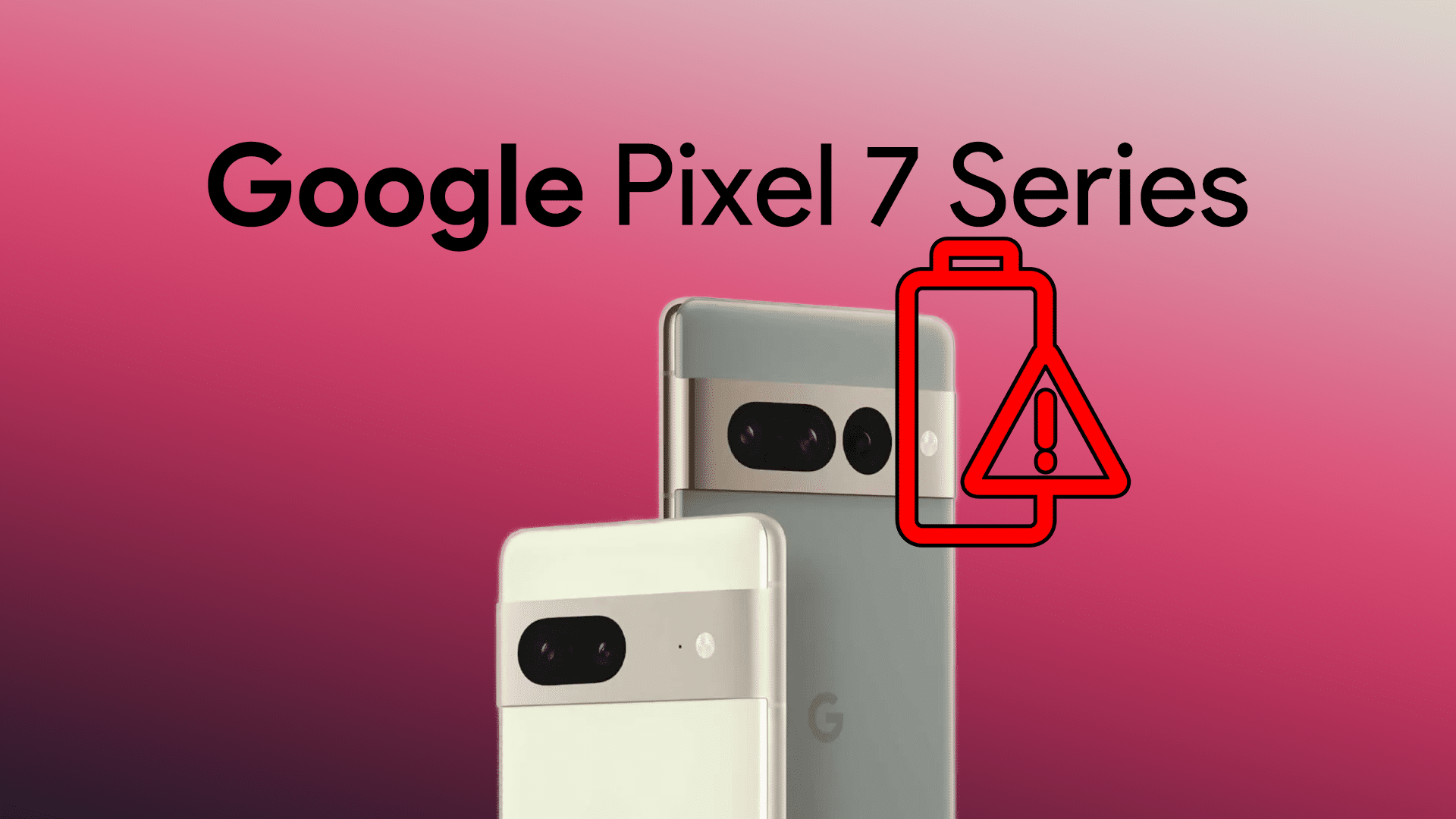
コメント