NVIDIAがTSMC 1.6nmプロセスを使う最初の顧客になる可能性
TSMCの最先端プロセスは、高性能かつ電力効率の高さが期待される一方で、歩留まりの低さやウェハー1枚あたりのコストが非常に高くなる傾向があります。そのため、これまでは小型のダイサイズかつ電力効率が重視されるAppleやQualcommなど、モバイル向けチップセットが最初の顧客となるのが一般的でした。
しかし、AI開発をめぐる熾烈な競争の中で、NVIDIAがこうしたトレンドを覆し、TSMCの最先端プロセスをいち早く採用する初の顧客になる可能性があることが明らかになりました。
NVIDIAが20年来の方針を転換。最先端プロセスを積極採用へ?
台湾の商工時報によるとNVIDIAはTSMCの次世代プロセスである1.6nmプロセス(A16)を採用に向けて協議が行われているようで、TSMC A16プロセスの採用を正式決定する最初の顧客になる可能性があることを明らかにしました。
NVIDIAは伝統的に、TSMCの最新プロセスが登場してすぐに飛びつくのではなく、プロセスが成熟し安定した段階で採用するという、比較的保守的な戦略を採ってきました。これは110nmプロセスの時代から続くもので、同社はプロセスの微細化よりも、GPUアーキテクチャーの改良によって性能向上を図ることを優先してきました。
しかし、AI分野での競争が激化する中、NVIDIAはこの長年の方針を転換する必要に迫られているようです。ライバルであるAMDなどの追い上げを受け、性能面で優位性を確保するためには、アーキテクチャーの改良だけでなく、最先端プロセスの利点も最大限に活用することが不可欠になったと考えられます。
2027年後半に登場? 1.6nmプロセス採用の次々世代GPU「Feynman」
TSMCにとってA16プロセスは、GAAFET(Gate-All-Around FET)トランジスタや、チップ裏面から電力を供給するSPR(Super Power Rail)といった革新的な技術を導入するプロセスになっており、現行の2nmに比べて多くの新技術が投入されるプロセスになっています。そのため、大幅なコスト増や低い歩留まりなどのリスクも付きまとうことになりますが、上手くいけばNVIDIAのアーキテクチャー刷新と共に大幅な性能向上が可能となり、猛追しているAMDに対して差を広げることが可能になります。
このTSMC A16は2026年後半から本格的な量産が開始される予定であり、NVIDIAが同プロセスを採用する製品は2027年後半から2028年初頭になると見られています。NVIDIAのロードマップに基づくとこの時期に登場する製品はRubinアーキテクチャーの後継にあたるFeynmanアーキテクチャーになると見られています。
ゲーミング向けで採用となれば値上がりは必須に
NVIDIAが投入するゲーミングおよびAI向けGPUは細かなGPUアーキテクチャーは異なるものの、製造プロセスは両者の間で同じ製造プロセスを採用する例が多く、Blackwell世代でもゲーミングとAI向けは共にTSMC 4nmが採用されています。そのため、もし仮にFeynmanアーキテクチャーでもゲーミングとAI向けが同じ製造プロセスを採用となれば特にダイサイズが大型化で、コストアップの影響を受けやすいGeForce RTX 7090などハイエンドモデルを中心に大幅な値上がりが必須と言え、現行RTX 5090以上の価格での販売が懸念されます。
一方で、TSMC A16は歩留まりや供給量に限りがある可能性も高いため、NVIDIAとしてはゲーミングとAIで採用する製造プロセスを変えると言う選択肢が現実的と言えますが、背反としてゲーミングとAIを同時に開発することによる開発費が増えるほか、製造キャパシティーを柔軟に割り当てると言うこともできなくなりますが、NVIDIAが製造プロセスの選定方法を大きく変える中で、ゲーミング向けGPUについてどのような考え方で開発が行われるのか、製造プロセスは性能として価格にも影響が大きく出るため、今後の動向に注目が集まります。
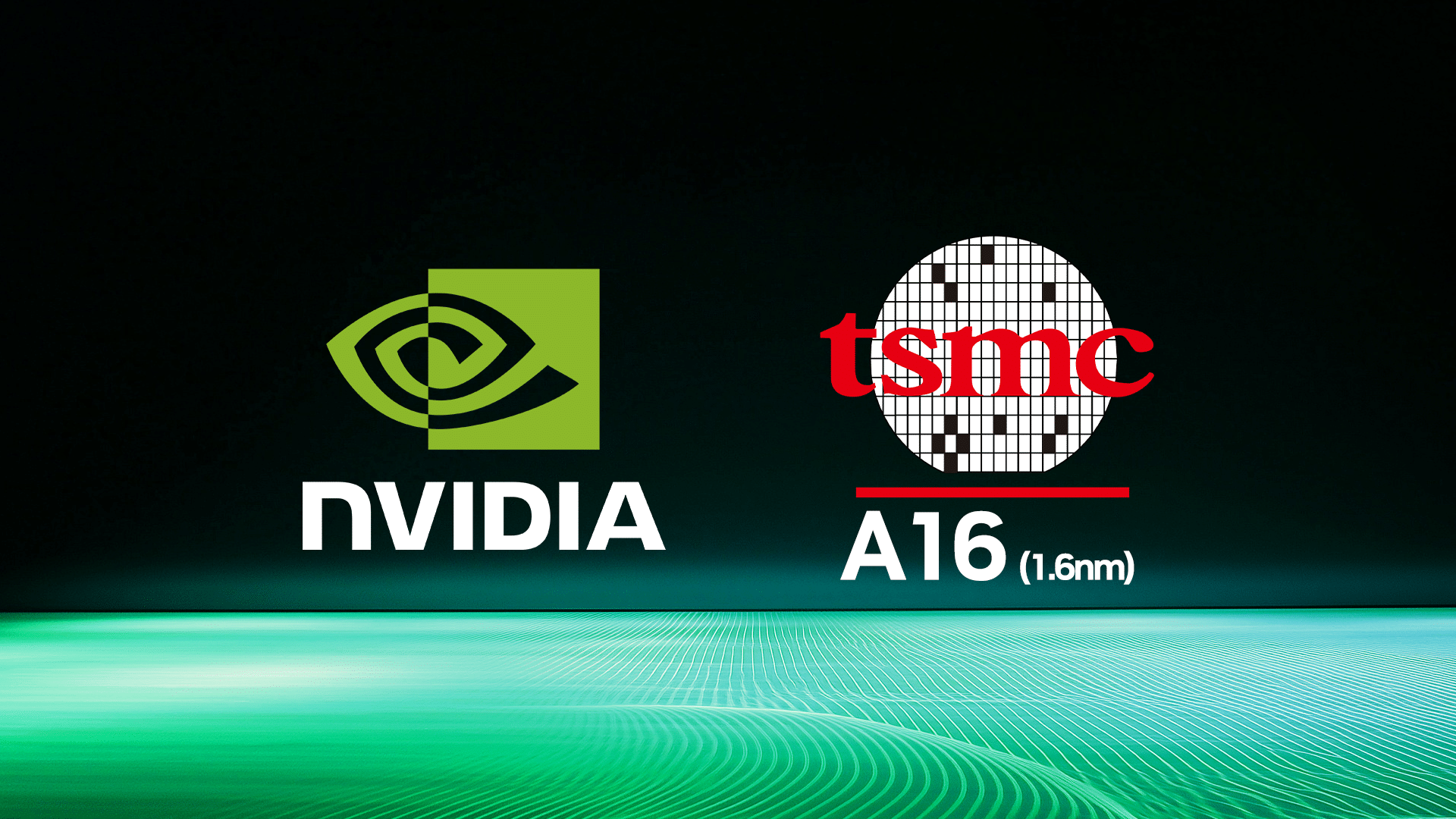








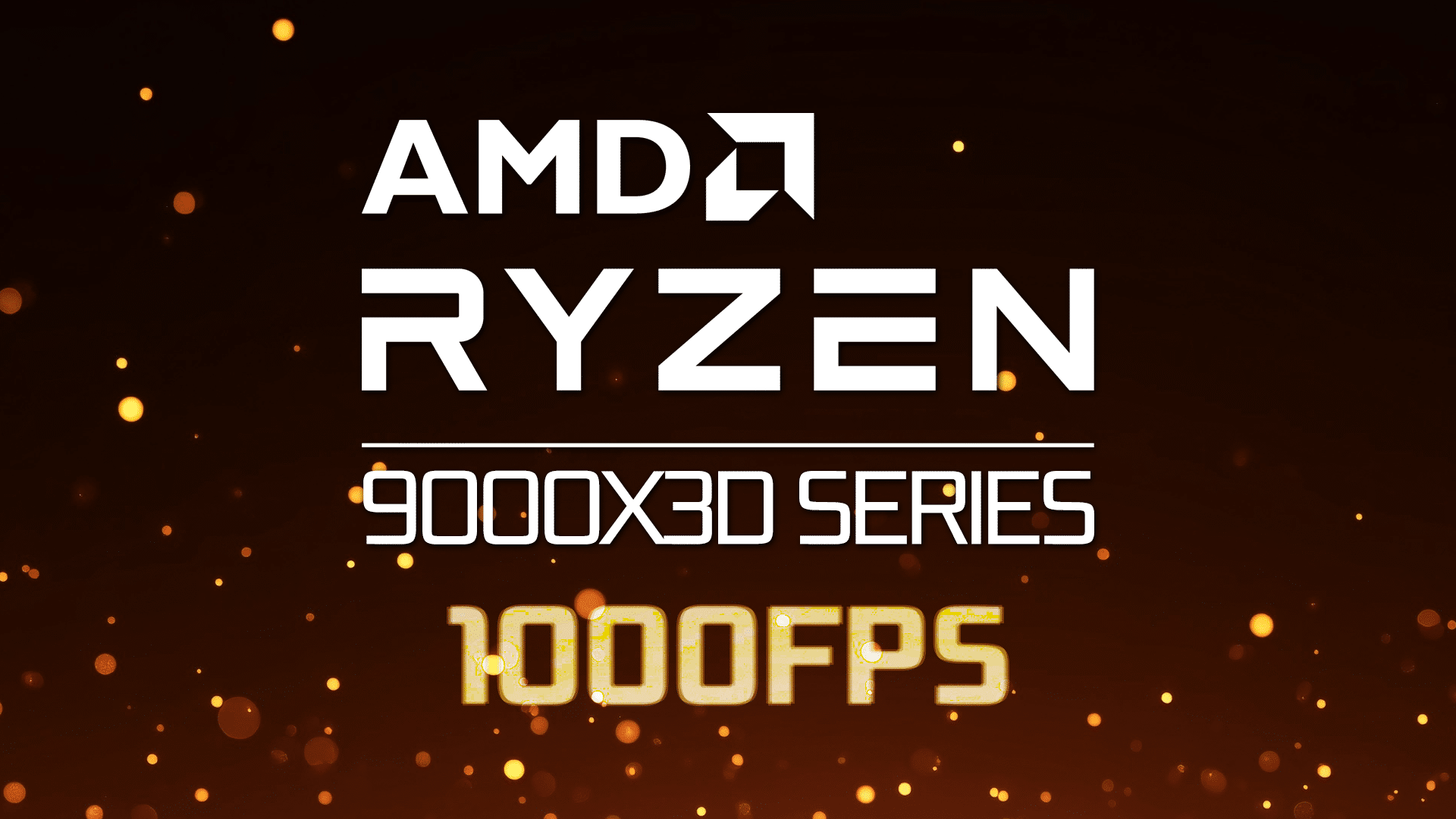
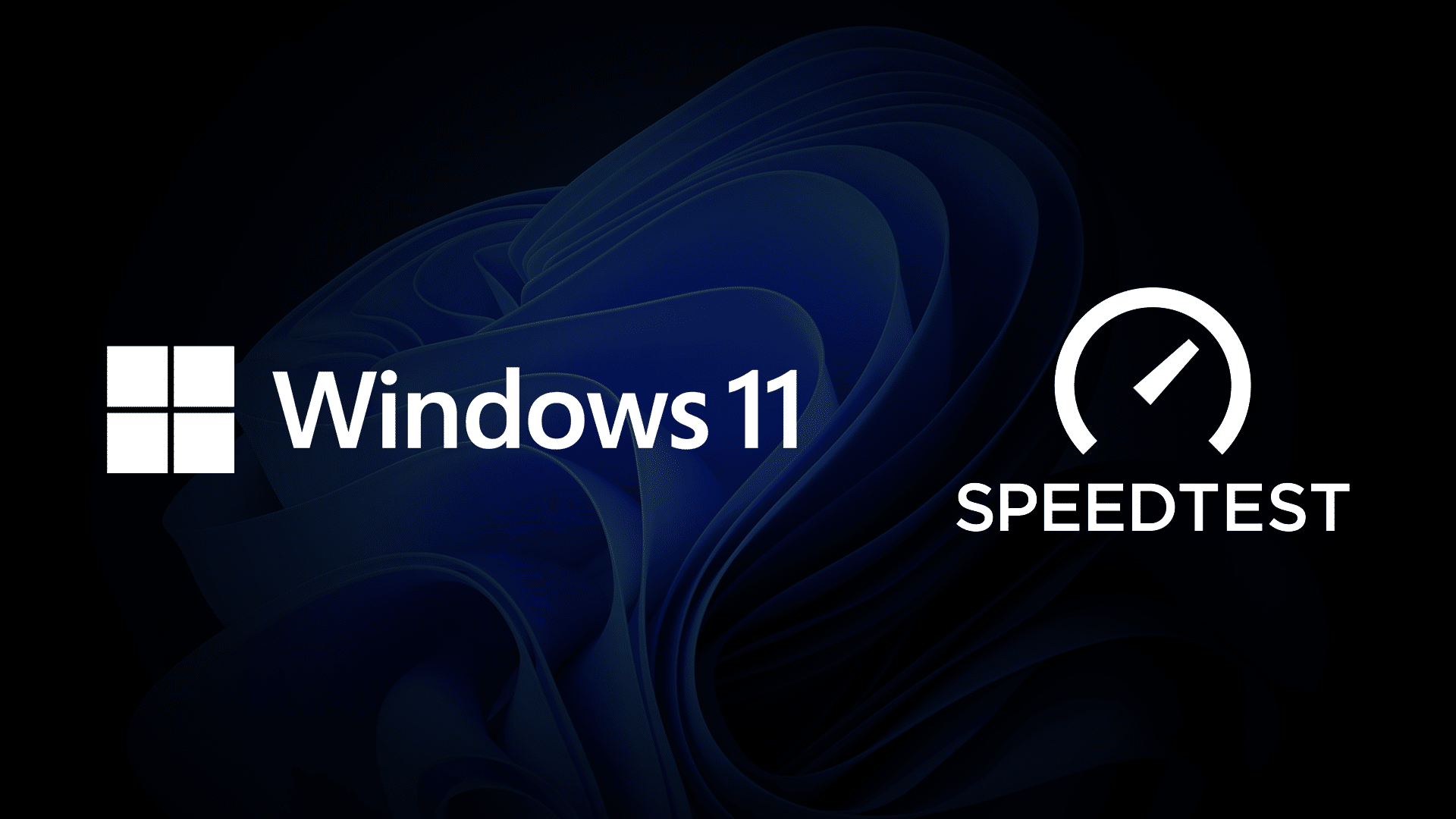
コメント