AMDがチップレット構造を採用したGPUを本格採用する可能性
現行のRDNA 4アーキテクチャ(Radeon RX 9000シリーズ)では、AMDはハイエンドでのNVIDIAとの正面対決を避け、ミドルレンジに注力する戦略を選びました。いっぽう次世代のRDNA 5では、ハイエンド復帰に加え、GeForce RTX 6090に対抗し得る最上位モデルを投入するとの噂もあり、頂上決戦の再来が期待されています。こうした性能強化とコンシューマー向けとして許容できる価格帯の両立に向け、CPUで成功した「チップレット」技術をGPUへ本格応用する動きが進んでいる可能性が浮上しました。
元Intelの著名アーキテクトのLinkedInプロフィールでAMD向けGPUチップレット開発を示唆
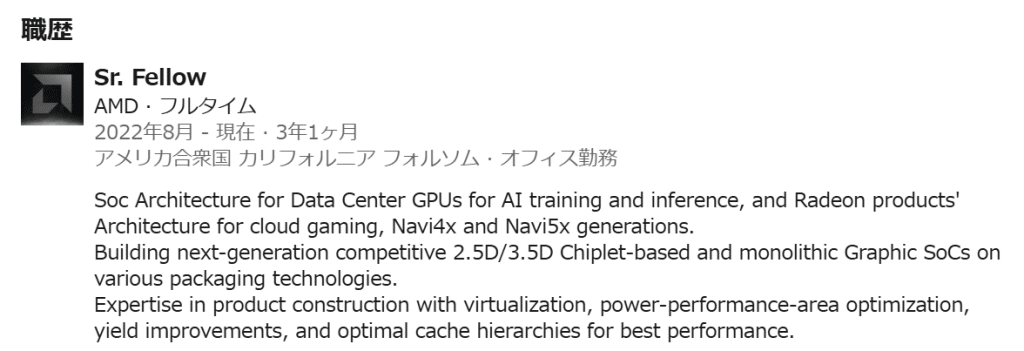
情報源は、AMDのシニアフェローおよびチーフSoCアーキテクトであるLaks Pappu氏のLinkedInプロフィールです。同氏は約25年にわたりIntelに在籍し、Arc AlchemistやBattlemageといったディスクリートGPU開発を率いた人物で、在籍時にはマルチタイルGPUの研究開発にも従事していました。
Pappu氏は、AMDではRDNA 5世代を示すNavi 5x系GPUのアーキテクチャ開発を牽引しているほか、2.5Dまたは3.5Dパッケージングを用いたチップレットおよびモノリシックダイのGPUチップ開発にも取り組んでいる旨を明らかにしています。これらの記述から、AMDが次世代GPUでチップレット適用を念頭に置いた開発体制を整えていることがうかがえます。
チップレット構造採用でコスト低減。NVIDIAに対して競争力を確保?
Pappu氏の職務内容ではNavi 5x開発とチップレットの研究開発は別の項目として記載されているため、RDNA 5で確実にチップレット構造が採用されるとは断定できません。しかし、近い将来登場するGPUはTSMC 3nmの採用などウェハーあたりのコストが非常に高くなるため、ダイサイズが巨大化しやすいハイエンドモデルではコンシューマー向けとして販売することが難しくなると見られています。
しかし、チップレット構造を採用できればダイサイズをAMDがCPUのRyzenシリーズで行っているように小型化することが可能になるほか、性能向上はチップレットを追加するだけで可能となるためモノリシックダイでハイエンドGPUを製造するよりもコストを大幅に下げることが可能になるほか、開発費も低減することが出来ます。
一方で、GPUは数千スレッドが低遅延で密に連携する特性を持つため、チップレット化のハードルは高いのも事実です。AMDも長らく研究を重ねてきたものの、完全な計算タイル分割には課題が残ります。そのため、まずは一部機能のみのチップレット化(例:メモリ/I/O系)でダイ縮小を図る段階的アプローチとなる可能性もあります。実例としては、RDNA 3がメモリコントローラ等を担うMCDを分離する構成を採用しましたが、RDNA 5ではどこまでチップレット化に踏み込めるのか、構造の革新性やコストパフォーマンスの向上など今後の動向に注目が集まります。
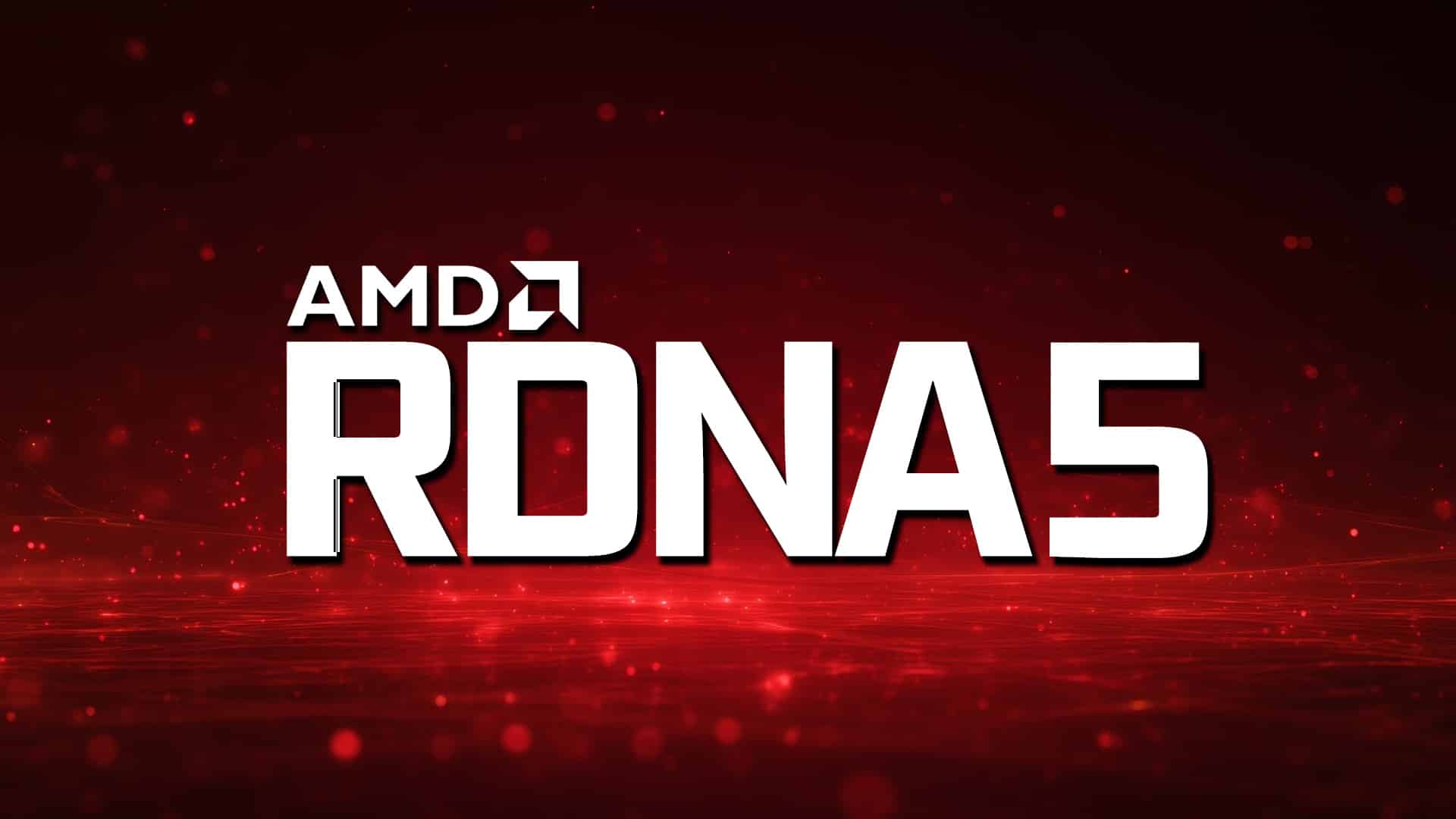

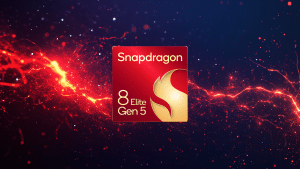
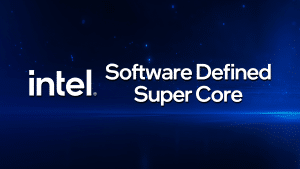

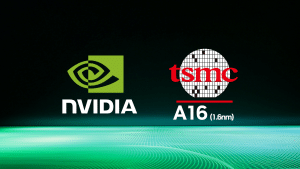



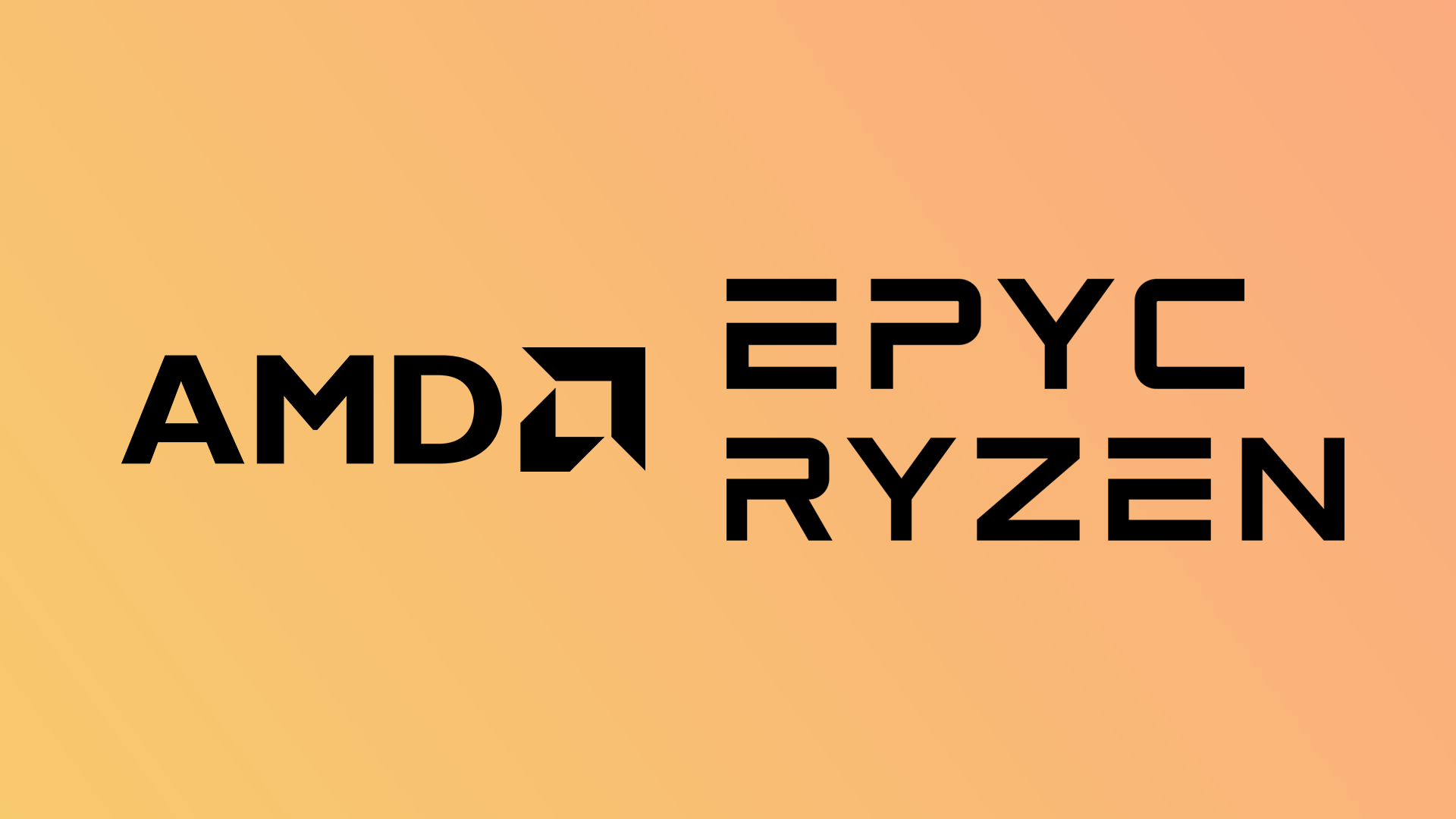

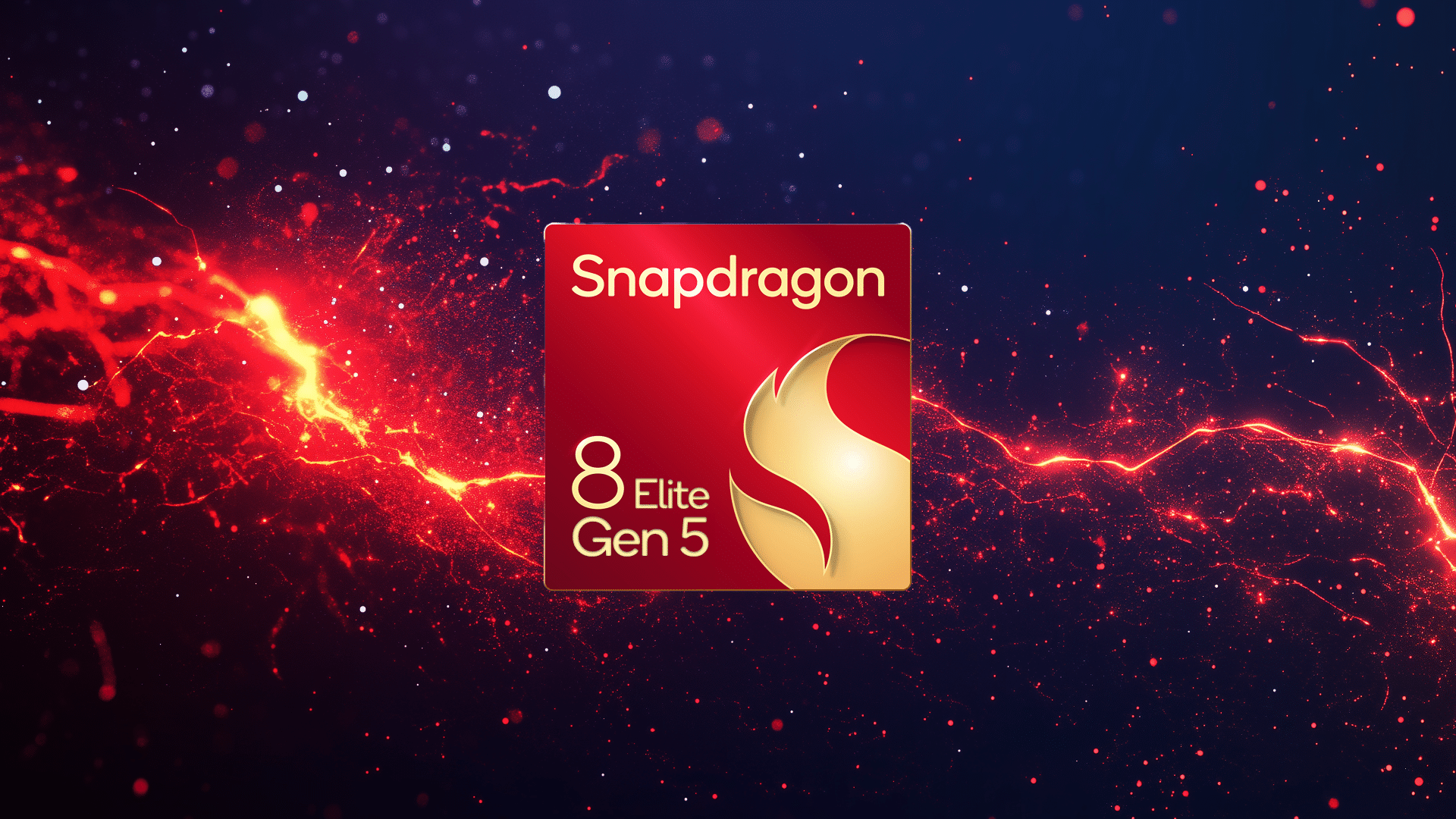
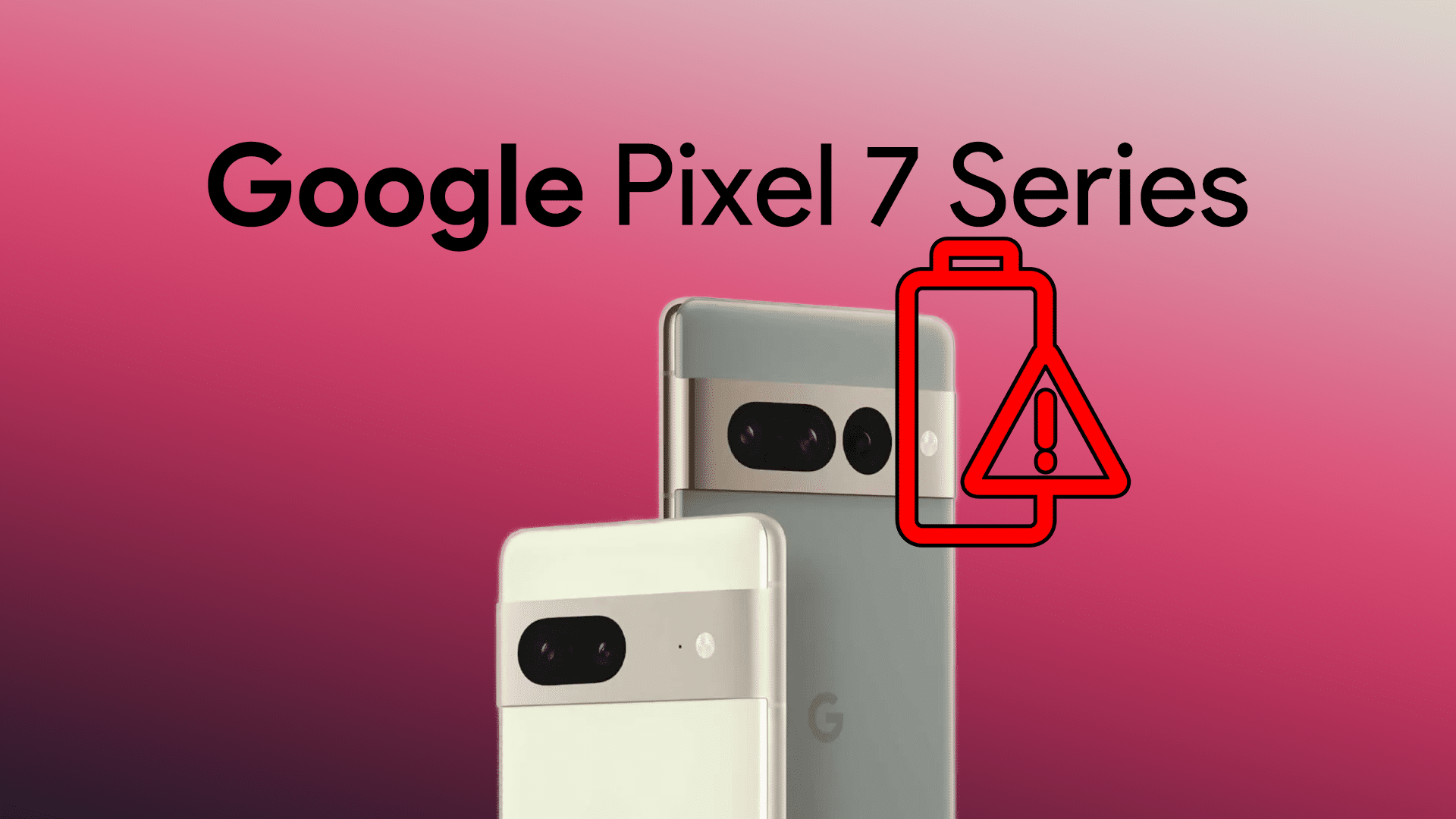
コメント